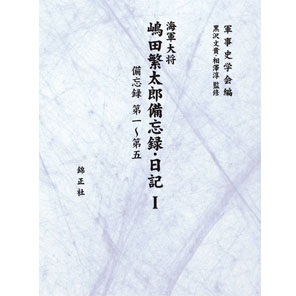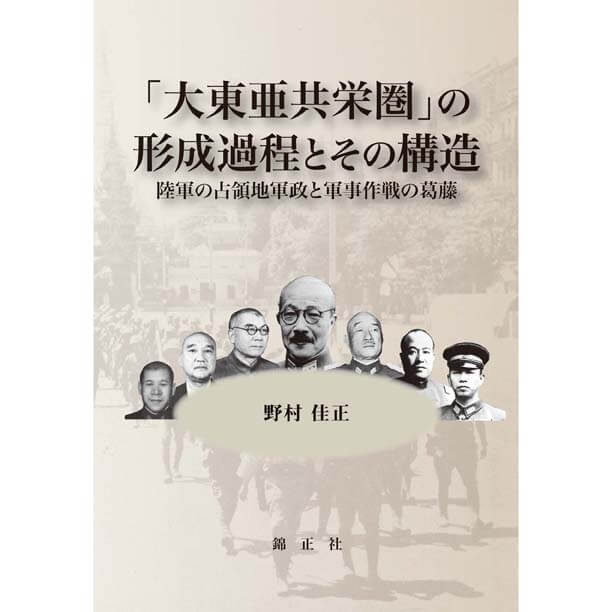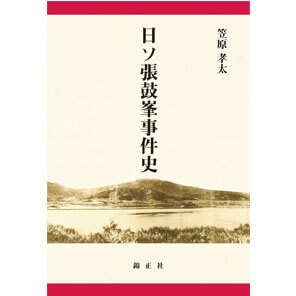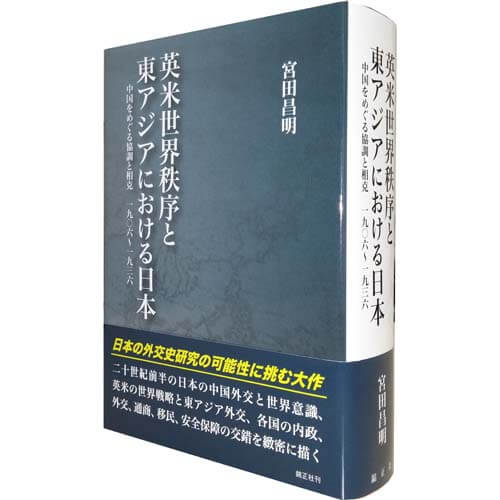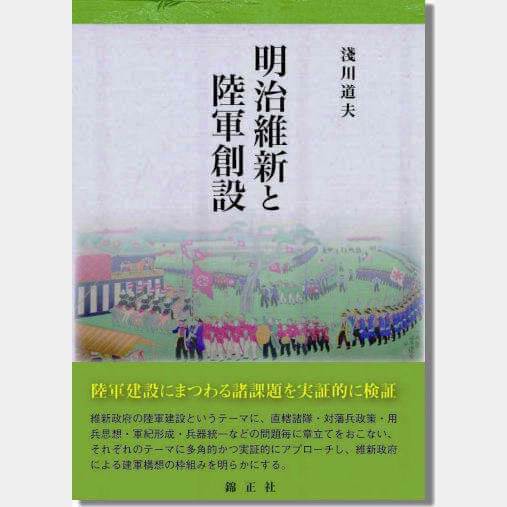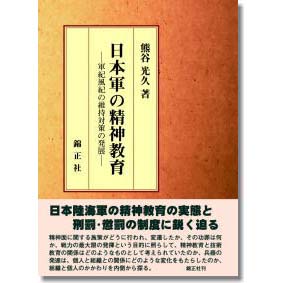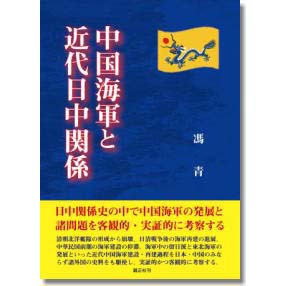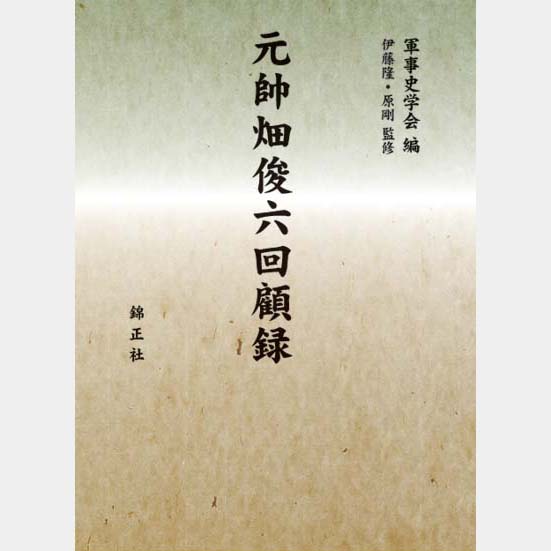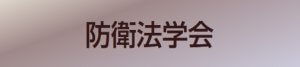機密戦争日誌《全二巻》〔新装版〕
―大本営陸軍部戦争指導班―
 |
著者 | 防衛研究所図書館所蔵 軍事史学会編 |
| 定価 | 22000円(10%税込) | |
| 本体 | 20000円(税別) | |
| 判型 | A5判 | |
| 体裁 | 上製本・セット函入 | |
| 発行日 | 平成20年5月1日 | |
| ISBN | 9784764603233 | |
| ページ数 | 800頁 |
参謀たちの生の声が伝わる貴重な史料
変転する戦局に応じて、天皇と政府、陸軍及び海軍が、政治・外交指導を含む総合的な戦争指導について、いかに考え、いかに実行しようとしたか?日々の克明な足跡がここに明かされる。
「機密戦争日誌」とは、大本営政府連絡会議の事務をも取り扱っていた大本営陸軍部戦争指導班(第二十班)の参謀が昭和十五年六月から昭和二十年八月まで日常の業務を交代で記述した業務日誌。
敗戦にあたり焼却司令が出される中、一人の将校が焼却に忍びなく隠匿するなど、様々な経緯を経て防衛研究所図書館に所蔵され終戦から半世紀を経た平成九年に一般公開された貴重な史料。
※本文は全て活字化し、原文のまま(カタカナ書き)とし、原則として旧字体は全て新字体に改めてあります。
| 刊行にあたって 軍事史学会会長・政策研究大学院大学教授 伊藤 隆 |
| 今回防衛庁防衛研究所所蔵の大本営陸軍部第二十班(戦争指導班)の昭和15年6月1日から20年8月1日に至る業務日誌「機密戦争日誌」を刊行することが出来たことは、本会にとっても、多くの研究者にとっても大きな慶びとする所である。元来大本営内の各部課でも業務日誌を作成していたと思われるが、現存するものはこの第二十班(戦争指導班)のもののみである。敗戦にあたり、書類焼却指令が出されていた中で、これが残存しえたのは一人の庶務将校が焼却に忍びなく、これを含む一連の文書を密かに隠匿したことによるのであって、今日となって我々はその恩恵に預かることが出来るのである。それが今日まで保存されてきた経緯については「解説」に譲るが、歴史史料の運命として深く考えさせられるものがある。 それらの文書の内、『杉山メモ』『敗戦の記録』として出版されたものが、どれだけ太平洋戦争期の研究に大きく貢献したかは言うまでもない。そして最後に残ったこの「機密戦争日誌」は、関係者の努力で、昨年(平成9年)十二月に全面公開されるに至り、早速本会として、その史料としての重要性に鑑み、編集委員会を組織して、刊行に向けての準備を始めた。波多野澄雄・赤木完爾・高橋久志・戸部良一・黒沢文貴・原剛・中尾裕次・庄司潤一郎・相澤淳・立川京一の諸氏がその任に当たった。この人々の献身的な努力によって今日の刊行に至ったのである。また刊行に当たって出版社の錦正社の人々の協力を得た。公開から出版にまで漕ぎ着けるのに役割を果たして下さった多くの人々に厚く御礼を申しあげる。 大本営陸軍部第二十班(戦争指導班)の位置付け、実際にこの「日誌」を作成した人々については、「解説」に詳しいのでここでは触れないが、多くの記録が失われた現在、この史料の持つ意味は極めて大きいと言わなければならない。かつてこの「日誌」は、服部卓四郎『大東亜戦争全史』や防衛研修所戦史部の『大東亜戦史叢書』の編纂に利用され、あるいは一部引用され、また「日誌」の執筆者の一人である種村佐孝が『大本営機密日誌』として、本「日誌」を一部利用しながら出版し、更には非公開であったにも拘わらず『歴史と人物』がその抜粋を連載したという事があった。従って、本「日誌」は多くの人々にその存在、ある程度までの内容を知られていた。しかしそれらが全文きちんとした校訂を経て出版されることによって誰しもが信頼できる史料として利用できるのである。 前に述べたように多くの史料が焼却された中で幸いに残存したこの「日誌」は、言うまでもなく大本営全体の記録ではなく、戦時の陸軍の戦争指導についての全貌を明らかにするものではないが、そうした限界にも拘わらず、第二十班が大本営政府連絡会議の事務をも担当していたという位置から考えて、太平洋戦争をめぐる軍事と政治を分析するための第一級の史料としての位置を持つものである事は疑いない。研究者を中心に本史料による研究の進展を期待するものである。 |
| 「機密戦争日誌」の刊行を慶ぶ 元大本営陸軍部参謀・伊藤忠商事特別顧問 瀬島 龍三 |
| この度、大本営陸軍部第二十班(戦争指導班)の業務日誌「機密戦争日誌」が刊行されることは、誠に慶ばしいことであります。私にとっても一入感慨深いものがあります。 私は、大東亜戦争開戦前から終戦の直前まで、大本営陸軍部作戦課に勤務し、陸軍全般作戦の企画立案などにあたっていたために、第二十班とも戦争指導面でそれなりに緊密な関係をもっていました。特に開戦前後の頃、同期生の盟友原四郎君が、少人数ながら戦争指導に関する事という重要職務を担当する第二十班の中で、東奔西走していた様子が、今でも目に浮かびます。 この日誌は、戦争指導に関して、政府・陸軍・海軍の事務担当者が調整した事項ならびに大本営政府連絡会議の議事などが記載されており、当時の政府と陸軍さらには海軍が、戦争指導についていかに考え、いかに実行しようとしていたかを知り得る第一級の史料であります。 より多くの方が、この日誌を読まれ、大東亜戦争について、より深く考えて頂くことを期待します。 |
推薦のことば
| 愛知工業大学客員教授・前軍事史学会会長 野村 実 |
| 防衛庁の戦史編纂官として私は、何冊かの『戦史叢書』を執筆した。 海軍関係でもっとも利用価値が高かった史料は、終戦のときの軍令部第一部甲部員(戦争指導担当)が、自信の金庫に保管していた歴代の甲部員が作成した機密の公文書であった。 今回、錦正社の創業六十周年記念企画として刊行される『機密戦争日誌』は、陸軍関係で右の海軍史料に対応する最重要史料である。 なおさらに、当時は陸軍が日本国内で最大の政治力を保有していたことと、執筆した戦争指導関係者が個人的な感情まで記入している部分があるので、海軍関係とは異なる歴史的意義を持っている。 さきに種村佐孝氏が個人的に刊行したことのある『大本営機密日誌』は、修文・削除・追加などがあるので、学術的には利用に耐えない。 本書の記念企画刊行を喜び、これにより国内・国外の研究がさらに進展することを期待している。 |
| 日本大学法学部教授 秦 郁彦 |
| これまでも、部分的に紹介されていた大本営機密戦争日誌の全文が、終戦から半世紀余を経てようやく公刊されるようになったのは喜ばしい。 戦時高等司令部勤務令では、機密作戦日誌を作成するよう定めていた。大本営(陸軍省や参謀本部)の部課でも、これに準じる日誌を作成する慣例になっていたが、第二次大戦期で現存するのは、戦争指導班(名称は第二十班、第十五課などと変わったが)の班員が交代で書きつぎ、戦後も米軍の接収を免れるため苦心して守りぬいたこの日誌だけであろう。 大本営の中枢である作戦課と戦争指導班の関係は微妙であった。建前は並列だが、後者の「理想論」は日々の戦闘指導を優先する前者の「現実主義」にとかく押されがちだった。その不満や批判は日誌のあちこちに顔を出している。そのせいで単調なお役所式作文の弊を免れている面があり、研究者にはかえってありがたい。 「戦史叢書」102官の刊行が終わってからすでに20年が過ぎた。新しい世代による大東亜戦史の見直しは、この機密戦争日誌の読み直しからスタートして欲しい。 |
| 作家 半藤 一利 |
| 想い起こすと、私がはじめてこの超一級の史料の原本を目にしたのは、1964(昭和39)年の秋のことであった。終戦を主題にした『日本のいちばん長い日』(文芸春秋刊)をかこうと、取材をすすめていたときである。元陸軍中佐で陸軍省軍務課員であった竹下正彦氏がそれを私に示し参考にするようにと親切さを示してくれた。しかし、氏は誠に上手に肝腎の一行を隠しおおせて見せてくれた。それは陸相阿南惟幾大将が、割腹の直前に「米内を切れ」といった一語の個所である。本が刊行されたしばらくたって私はその事実を知ったが手遅れもいいところで、いらい咽喉にささったトゲのように私はそのことを気に病まなければならなかった。 その国家観において忠誠観念において、民間人ならともかく同じ軍人として、阿南は米内光政海相に許せぬ卑劣さを感じていた。終戦劇はそうした日本人の精神構造を複雑に綾なしてすすめられた。「米内を切れ」の一言はその象徴であった。 『機密戦争日誌』は昭和の日本戦争指導について知り得る第一級の史料である。が、このようにこれを記述した参謀の貴重な体験や個人的感情もかきこまれ、陸軍を超えて、それ自体が昭和日本の精神史ともなっている。その全文公開を心から喜んでいる。 |
| 作家 保坂 正康 |
| 本書刊行の報にふれたとき、私は気持ちの高まりを覚えた。長年、待ちに待っていたからである。昭和史に限らず日本の近現代史に感心をもつ者なら、この書がどれほどの価値があるか、この書からいかに多くの事実を学びとれるか、をよく知っている。第一級の史料であることはいうまでもなく、近現代史を正確に理解する上での道標の役を果たすこともよく知っている。 大本営陸軍部の第二〇班(戦争指導班)は、設置以来、組織は小なりといえど、その役割は大きかった。主に戦争指導に関する事務を取り扱ったが、具体的には大本営政府連絡会議の事務に携わったため、班員たちは昭和十年代の政治と軍事の両輪がどのように動いたかを知る立場にあった。その内実を綴った日誌が、これまでに六分の一程度公表され、近年になって全面公開されてはいたが、公刊されてこそこの史料は意味を持つ。私は、昭和陸軍の国策決定のプロセスに感心をもっているが、本書によって新たな目が開かれるとの期待に胸がはずむ。取材を通じて知った班員の当時の考えも確かめたいと想う。 過去の歴史の継承は次代の者の責任である。本書が刊行されることで、私の世代の責任が次への世代に果たせたこと、それを編者や発行者とともに喜びたいと痛切に思う。 |